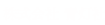叢書 魂の脱植民地化 6
副題 東アジアの「余白」を生きる
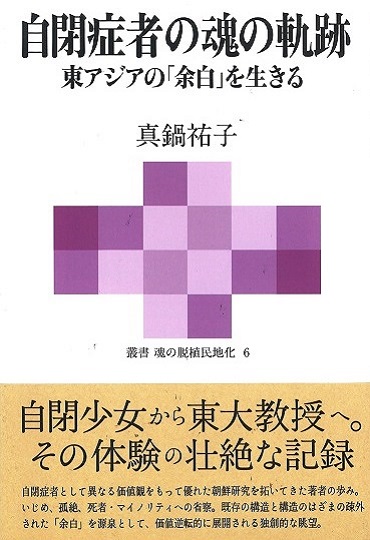
著者:真鍋祐子
ISBN:978-4-86228-077-0 C0036
定価 2,500円+税 336ページ
ジャンル[社会・エッセイ]
発売日 2014年12月22日
紹介
自閉少女から東大教授へ。その壮絶な記録。
・小学校時代、担任教師や級友たちのいじめ。
・院生時代のアカデミック・ハラスメント。
・30歳過ぎまで、出しても出しても送り返されてくる大学への公募書類。その数、30余。
そんな絶望の日々、心酔し、狂い死ぬほど笑ったナンセンスソング、クレイジー・キャッツの「ホンダラ行進曲」。
・学会でタブーとされていた韓国民主化運動における死者に注目した独創的な博士論文が評価され、大学から助教授就任の打診をうける。
・自閉症者としての著者自身の生と切り結びながら、死者やマイノリティへの省察をすすめる。
既存の構造と構造のはざまの疎外された「余白」を源泉として、価値逆転的に展開される独創的な眺望。
・自閉症者にかぎらず、さまざまなマイノリティにも開かれる瞠目すべき実践と思索。
目次
序 別府晴海
はじめに──偶然性を生きる
Ⅰ「自閉的な知」の獲得と構造主義
一章 偶然にも最悪な自閉少女
二章 自閉症者と通過儀礼性
三章 「自己スティグマ化」の過程を生きる
四章 与えられる「構造化」/フィードバックされる「構造化」
Ⅱ 死者の「かそけきことば」を聴く
五章 死者たちの追憶
六章 死者の声をたずねて
七章 「死の壁」を超える
Ⅲ 東アジアの「余白」を生きる
八章 ふたつのハラスメント体験から
九章 東アジアの「余白」に立つ
十章 死者とともなる社会
おわりに──竹下文雄さんに捧げる
著者プロフィール
真鍋祐子 (まなべ・ゆうこ)
東京大学東洋文化研究所教授。1963年北九州市生まれ。奈良教育大学卒業、筑波大学大学院博士課程社会科学研究科修了。社会学博士。
著書『キャンパスに見る異文化―韓国暮らしの素描』『烈士の誕生―韓国の民衆運動における「恨」の力学』(以上、平河出版社)『増補 光州事件で読む現代韓国』(平凡社) ほか
訳書『恨の人類学』(崔吉城著、平河出版社)
はじめに
二〇一二年三月、私が初めて主催した国際シンポジウム「コリアン・ディアスポラの記憶を手繰る──『犠牲の状況』を超えて」に、CMディレクター、映画監督のグスーヨン(具秀然)さんをお招きした。以下はシンポジウム後に送っていただいた講演の草稿である。
山口県の下関で、在日一世の父親と在日二世の母親の間に在日二世として生まれました。
別に望んだわけではないんですが、在日として生まれてしまったわけです。
ボクが幼稚園に入るときに、通名を使うかどうかを父親と母親が話し合ったそうです。父親は、ボクが大きくなって通名と本名がある理由を聞かれたときに、ちゃんとした答えが出来ないだろう、ということで、ボクには通名がありません。
最初からグスーヨンです。
小学校から中学校と例外に漏れずイジメなんかにあったりしながら、この偶然にも在日に生まれた少年は育っていきました。
下関という場所が、人口二五万人のうち一万五千人が在日という特徴のある街だったので、必然的に否応なくずっとケンカばかりしていました。
ホントは、ケンカなんかやりたくないんですけど、そういう街だったんです。
受験に失敗して、お金もないので仕方なく東京の夜間の専門学校に行きました。グラフィックデザインをやりたかったんですね。
そして、たくさんの就職試験を受けて、ずいぶん落ちましたが、二三歳の時、やっとのことで、デザイン会社に就職しました。
業界でも有名な会社でした。
そこで、CMの世界に入り、映像の監督を目指すようになりました。
また、CM監督の試験を受けまくって、二六歳の時にCM監督デビューです。
日本人と違う価値観を持っているというのが、この業界では重宝されたのでした。二〇代でCMの賞を取りまくって、まさに天狗になっちゃいました。
偶然にも在日に生まれた少年が、その偶然を幸運だと思うようになったのは、その頃からです。
それから二五年たった今、小説を書いたり、映画を撮ったり、音楽の作詞をしたりと、やりたいことをやりたい放題やってきました。
世間の人に申し訳ないと思うほど、なんの苦労もなく、ホントに楽しい人生を送らせていただいています。
そう思うようにしています。
それは、まさに偶然にも在日に生まれたからなのです。
ボクのテーマは、「折り合い」です。
「分かり合う」なんてのは、ほとんど出来っこない。
ボクの三〇年間連れ添っている奥様とでさえ、分かり合えていないのですから、仕事関係とか、ましてや国と国との関係など無理に決まっています。
そこにある「不条理」や「理不尽」と分かり合うなんてことは、出来ないのです。
ホントは「折り合い」なんてのもつくかどうかわかりませんが、分かり合うことよりはずっとハードルが低いでしょう。
「偶然にも最悪な少年」は、二冊目の小説を映画化したものですが、この主人公の少年が頭の悪いなりに、自分や家族や社会と、どうやって折り合いをつけようとしたのかを見てあげてください。
一見すれば偽悪的にも映る文体だが、裏を返せば自分の生きて来し方を公に普遍化して語ることへの含羞を、彼独自の言葉で語るとこうなるのだろう。しかし「偶然にも在日に生まれた」自身の来歴を語りつつ、だがそうした偶然性こそが実は幸運であったと言い、人はそうした偶然性を生きるなかでその折々に出会う他者たちと「折り合う」のであって、人と人、まして国と国が「分かり合う」ことなどできないのだと説く、その飄々とながらも鋭利な語り口に私は深く心打たれた。そして映画「偶然にも最悪な少年」(二〇〇三年)から私なりに受け取ったメッセージと、これを撮った監督をぜひシンポジウムにと考えた自分の直感に、おおよそ狂いがなかったことを確信して安堵した。
同じ年の暮れ、在日コリアンの院生たちも受講する私のゼミに、ふたたびグスーヨン監督を招聘した。そのとき「二〇歳からの三〇年余り、週に十冊の本を読み、十枚のレコードを聴き、十本の映画を見る、というノルマを自分に課してきて、今まで一度も欠かしたことがない」という話を聞いた。「やりたいことをやりたい放題やってきました」と軽やかに語る言葉の裏には、このように心と精神を尽くした学びと思索の日々が凝縮されていたのである。
かつて「在日」を生きることは、マジョリティである日本人の想像をはるかに超えて、偶然性という要因が大きく作用したにちがいない。就職、昇進、結婚など、人生の節目ごとに国籍と差別の問題が立ちはだかる。はなからセーフティ・ネットの網の目にかかることなく、ホスト国の政治や経済の影響をかぶればただちに荒波に放り出される。そうやって多くの在日コリアンが、変則的な生き方を余儀なくされてきたにちがいない。これは今でもそうだろう。それでもこの俗世で生きていくには、ふりかかる理不尽をただ「理不尽だ」と叫び、正義を語るだけでは始まらない。理不尽な現実と折り合いながら、むしろ「日本人と違う価値観」を強みにできるしなやかさとしたたかさが必要なのだ。では、その強みとは何なのか。これを探し求める試行錯誤の道のりが、比類なきその人だけの人格を構成するのだと私は思う。
このように考えると、どことなく自閉症、非定型発達、発達障害などと呼ばれる人たちの、決して定型化されえない人生行路にも重なるように思われてきた。当事者である高森明はSR(スロー・ランナー)を自称しつつ、次のように述べている。
「出口は複数あり、その子どもが迷宮の中でどんな探索活動を繰り広げたかによって、全く異なる出口に到達することになる。その到達する過程、到達した出口によって形成していくのがその人の個性である。個性は生まれつきの特徴ではなく、その人が探索活動を展開していく過程で後天的に獲得していく特徴である。」(高森、二〇〇七:八一)
もっとも、こうした人生の一回性はSRに限られた話ではない。試行錯誤しながらそれぞれの出口に到達し、かけがえのない個性を形成していくことは、多かれ少なかれどの子どもにもいえることである。それでもなおSRの子どもたちは、より道なき道を、個別にあてがわれた狭き門を手探りしながら、前例なき出口をめざして与えられた生を歩き抜かなくてはならない。子どもの発達段階は社会化のプロセスと不可分の関係にあり、社会は多数派である定型発達に対しては、文化的にパターン化された生き方モデルを提供する。一方、発達面でのマイノリティであるSRは、ある部分は突出した発達を示しながらも、別のある部分は平均にはるか及ばないという発達の凸凹によって、社会化が困難であることが多い。世界の認知の仕方がよく言えば独創的、しかし多数派である定型発達を尺度にすれば歪んでいるので、社会との交流や交渉に軋みが生じやすい。こうして自閉症児はしばしば虐待やいじめの的となり、青年期になると社会性やコミュニケーションに関連して独特の「生きづらさ」を訴えるようになる。しかも発達凸凹の度合いには個人差があるので、同じSRでも先例はほとんど参考にならない。
「SRには手本がない。異なる生物的特性を持つがために模倣すべき大人が存在しないのである。これは恐ろしく時間のかかる探索活動である。」(高森、二〇〇七:八二)
高森のこの言葉ほど在日コリアンとSRの接点を言い表したものはない。在日コリアンの子どもは生まれながらに複数の「社会」にまたがりながら成長するので、その社会化を単線的にとらえることはできないだろう。また外在的な状況の大変化によって生き方の枠組が揺るがされ、そのつど自分の行くべき道を探索しなくてはならないだろう。それゆえ尊敬するべき先達はいるにしても、その生き方じたいをパターン化して「模倣すべき大人が存在しない」のではないだろうか。しかし、だからこそ誰もが歩まなかった自分だけの道を探り当て、「日本人と違う価値観」を武器に駆け上がっていく幸運も開けるはずだ。それがグスーヨンという先例であろう。つまりこれは「偶然にも最悪」でありながら、「偶然にも幸運」な一回性・偶然性の生を生きるという特権だ。裏返せば、どんなにグスーヨンの模倣をしても、誰もグスーヨンにはなれないのである。そしてこのことは私も含めたSRにも、おそらく当てはまるはずである。
自閉症者という自己認識に立ちながら、幼児期から現在にいたるライフヒストリーと、研究者を目指しての試行錯誤の日々を綴ったⅠ部は、まさに「SRには手本がない。(略)これは恐ろしく時間のかかる探索活動である」という高森の指摘を裏付けるような内容になっていると思う。また探索活動の途上で経験した出来事や出会った人びと、また研究の途上で遭遇したもろもろのエピソードは、廻りめぐって「私」という人格を構成することになったと思われる。そのなかでも特に、Ⅱ部では死や死者にかかわって巡らせた省察を中心に、Ⅲ部では韓国や中国の調査地で出会った非業の死者、民主化運動の犠牲者、またマイノリティをめぐる研究の一端を振り返りながら、これらが自閉症者としての私の生とどのように切り結ばれながら思索されてきたのかを、自己内省的に記述する。
つまり本書は私というひとりの朝鮮研究者を俎上に載せ、他者とは違う価値観によった研究の軌跡を、自分自身の魂の軌跡と重ね合わせながら記述するものである。在日コリアンからSRへという発想の飛躍は、読み手には突飛に見えるかもしれない。だが「在日」を含めた朝鮮民族との出会いは私の仕事の根幹をなすものであり、SRというのは他の同業者とは異なる価値観をもって独自の朝鮮研究を進めてきた私自身の属性にかかわるものである。どちらがなくても現在の私はありえないし、むしろこの両者が出会うところに私の研究の独自性があるのだと思う。その合流地点にあるのが本叢書のタイトルになっている「魂の脱植民地化」である。それは権力関係の内在化を強いられた「魂の植民地化」にあらがうものたちが、既存の構造から疎外され、吹き溜まっていく構造と構造のはざまの「余白」に生じた律動的力である。「偶然にも最悪」でありながら「偶然にも幸運」という価値逆転的な境涯は、そうした「余白」にこそ最深の源泉をもつ。
私の感触では、これこそが「魂の脱植民地化」の先に展開されるべき眺望であり、本書はそのことを証しようとするものである。